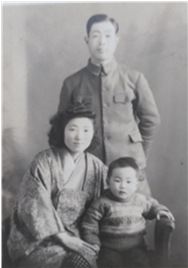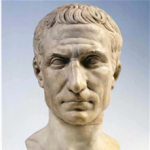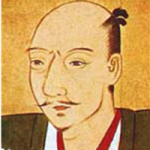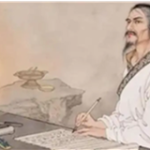2025年4月~2026年3月
2025(R7).10.31 ― 凛とした尊敬する叔父101歳 ― (第 150 号)
 |
1年ぶりで叔父(義理の叔父で叔母の夫)のTUさんを奥州市内のグループホームに訪問した。1年前は100歳のお祝いに参上した形であるが、尊敬する大恩ある叔父なので毎年1回はご挨拶することにしていた。
グループホーム内には入所者がみんなで寄り集まる広いホールとは別に一人一人の部屋があり、そこで訪問者は様々話をするのである。本人は車いすこそ使っているがすこぶる元気そうで、受け答えも一定レベルでは可能である。
何よりもその凛とした姿勢に感動すら覚えた。まず現役時代からの腕時計を左手に嵌め、胸にはこれも現役の時からの習慣でもある手帳とペンを左胸のポケットにしっかり指し込んでいる。手帳に何か書き込んでいるかは別として、「生涯現役」のそのスタイルが、本人の若さを保っているようである。私も将来そうありたいと思った。
TU叔父は、農業高校教員としてスタートし、若くして全国版の教科書「総合農業」の執筆代表になった程であり、53歳で高校長となり、3校を歴任している。退任後の高野長英記念館長時代、来館者からよく長英の手紙の読み方を質問され、説明側が分からないのは残念ということで、急遽古文書研究会に入って勉強を始め、遂に中学生でもわかる「高野長英の手紙」を発刊した。物事をおろそかにせず、熱心に地道に取組み、遂に成し遂げる人であり、敬意を禁じ得ない。
私がかつて奥州市最初の市長選挙に立候補した際、TU叔父さんには親戚の故をもって後援会幹部をお務め頂いたが、大勢の教え子の方々にも声を掛けるなど多大のお力添えを賜り、当選への道を開いていただいた。市長就任後に、ある教え子の方から、「TU先生から何十年ぶりに電話を頂き、生徒時代の何かまずいことでも思い出されてお叱りを受けるかと恐る恐る聞いたら、相原候補を宜しくとの話であった」と伺った。ご恩は尽きない。
TU叔父は、誰でも知っている自転車の乗りの名手である。軽快にまるで体の一部のように乗りこなし、九十代も続けられ、ついぞ転倒事故も起こさなかった。ただ、体調を崩して施設に移ることになったため、架け替え後の新小谷木橋(かつて毎日のように通った)を愛用の自転車で走破できていないことは心残りであろうと察している。
2025(R7).9.30 ― 「わが来し方―壮年期まで」を書き終えて ― (第 149 号)
これまで出版した3冊の著述集においては、正面から自分史的な内容を盛り込まなかった。今回第Ⅳ集作成に当たり、「わが来し方(壮年期まで)」と題して記すこととしたのは、これまでにない特色としたかったからである。この観点からは第Ⅲ集においては「滝沢村助役心象スケッチ」を著している。
もう一つには、やはり、そろそろ生まれてからのことを印象深く振り返り、子孫他に伝えつつ、育んでいただいた人々や地域等に感謝の意を申し述べるべきと感じたからである。
ところでペンを進める上で痛感したことがある。これまで第Ⅲ集までに掲載した内容は、ほとんど既に調査・推敲した上にホームページ等上に発表したものであり、改めて事実関係などを検証することはほとんど必要がなく、そのまま写し取り、構想案に従って選択し、移植していくような作業であった。
ところが今回の一代記的なものは既に何かに整理し、順序だてて書いたものがなく、思い出や記憶をたどる作業であり、その事実関係を証明する資料が特に無い、ある意味不確かな世界を切り分けていくような仕事でもあった。
このため、父が著作の形で残してくれた相原家の系譜と出来事の記述に頼ったりし、また自由奔放に、自らの心にしっかり残っている記憶をその時期の象徴として書き表す作業の連続となった。
この項の実質のスタートともいえる、祖父藤治郎との出だしの一節を紹介したい。
「記憶の始めは祖父藤治郎と祖母テルヨの部屋に寝ていたことだ。両親と妹は奥の部屋に寝ていた。父は県家畜保健衛生所勤務の獣医で忙しくあまり家におらず、また、我が家の伝統というか男親は息子と頻繁に会話する風潮がなかったので、祖父と話すことの方が多く、父親のような存在でもあった。食糧事務所長を退任し、家業の農業として米作り、ブドウ栽培に朝から晩まで精を出していた。いつも祖父の足の温りを感じながら、寝ていたので、私が、後年30代の大人になってから祖父の逝去に立ち会った際、次第に祖父の足が冷たくなっていくことに衝撃と悲しみが込み上げたことを思い出す。」
およそ1年かけてようやく書き上げた。第Ⅳ集の出版は1年後くらいを予定している。その際は、ホームページでネットにも内容を公開するので、是非楽しみにお待ちいただきたい。
2025(R7).8.31 ― 94歳の初出版 ― (第 148 号)
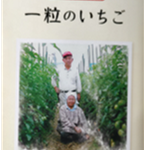 |
 |
親類の吉田英子さん(妻美智子の叔父である故重雄さんの妻。94歳)が「一粒のいちご」(四六判166頁)を出版された(2025年7月)。ずっと(30年以上)NHK通信文章教室を受講されていて、最近文章教室の先生(花巻の学び学園で教えている野中康行氏)にたくさんの原稿を読んでいただいたところ、「作品ひとつひとつに吉田さんの人生が語られている。これがこのまま埋もれてしまってはもったいない。本にまとめてみたらどうですか?吉田さんがこの世に存在したという証にもなりますよ」と勧められてのこと。
94歳での初出版とは驚異的でもある。私の父正毅は88歳で最後の出版(7冊目)をしたが、90歳を過ぎてからは知的作業をやめたせいかどんどん正確な記憶、表現から遠ざかっていった気がする。その点、英子さんは継続してきたことが年齢の壁をも乗り越えることにつながったかもしれない。お手本となる。
内容的には家族を中心に身の回りの人々、家事のこと、若い頃から一貫して取り組んできた農作業のことなどを飾ることなく、新鮮に感じた印象を添えてありのまま語る風である。書き溜めた200編ほどの中からNHK通信文章教室で比較的に高評価を得たものを載せたということで、文章としてもまとまっている。字数は1編1,300~1,400字程度で読みやすい。
題名の「一粒のいちご」の項があり、著者本人が心を込めた一つと思われる。最近逝去した妹が永年イチゴ栽培していたが、病に倒れる直前の苗がうまく育たなかったということで、姉の英子さんが世話をし、その苗を畑の草捨て場に捨てて忘れていた。その後まもなく妹が逝去し(9月)、翌年6月になったある日、ふと畑の捨て場に一粒だけのイチゴの実を見つけ、何気なくエプロンのポケットに入れた。不思議に思いながら、それを取り出して見つめるうち、さきのいきさつを思い出し、これは亡くなった妹からの贈り物と思えてきた。イチゴを口に入れたとたん、涙があふれてきたという内容である。読ませる力あり。
1週間ほどで読み終え、ハガキで次のように礼状をしたためた。
「吉田英子様 ご著書「一粒のいちご」ありがとうございました。優しく、わかりやすく、しかも正確な内容を伝えるものであり、感服いたしました。ご主人重雄さんとの掛け合い、写真を懐かしく拝見しました。ご健康で「書く」歩みを続けられますようお祈りしております。相原正明 美智子 R7.8.9」
後日談となるが、英子さんは「年だからもう書くのは辞めようと思っていたが、相原さんからのハガキを読み、思い直して再度文章教室に通うことにした」と私の妻に話したとのことである。
2025(R7).7.31 ― 人の心をとらえる文 ― (第 147 号)
 |
 |
今年も地元新聞社の「啄木・賢治のふるさと」随筆賞が発表された。最優秀賞はTKさんの「六十六のお祝いに」であり、選評欄には、「子供のころは母親の地味な料理が恥ずかしかった。けれども大人になると、それが旬の食材を生かし、手間をかけたものだったことがわかる。母が亡くなって食卓は一変した。並ぶのは冷凍食品ばかり。料理に挑戦しなくては。文章も巧みで読ませるし構成もいい。」とあった。
私が着目したのは、受賞者本人の「これまで挑戦してきた中で最も力が抜け、自然体で書けた。評価や賞を気にせず感じたことを正直に書いた。」というくだりである。
もう一人、「松次郎のこと」で優秀賞となったSKさんの受賞の言葉である。この方は作家くどうれいんさんの母親であり、俳人でもある。選評は、「端的な表現で、揺らぎない強さがある。恰幅がいい強面の祖父。年の瀬には附録付きの児童雑誌を届けてくれる。年に一回の雑誌が嬉しくて、たまらなかった。祖父はまもなくして亡くなった。本当のところ、どんな人だったのか分からない。ひとりの人間を理解することの難しさ。最後の一文が深い余韻を残す。」であった。
こちらは受賞の言葉に「応募しようと書いていた作品はほかにあったが、なぜか締め切り間近になって祖父のことが頭に浮かび、一気に書き上げた。」とあった。
この受賞者お二人の共通として感じられるのは、どうしても気になるはずの周りの評価を気にしないことにし、題材も賞に相応しいかどうかといったことを思い煩わず、自然体でふと心に浮かんだことを、一気に書き上げたというイメージである。そうであればこそ心の底から自分も気付かないうちにマグマのように湧き上がる熱流がほとばしり、それが本人も気付かぬうちに他の人々を引き込み感動させるのだと思う。賞の選者はその代弁者である。
私もかつて句会でなかなか提出句を拾ってもらえず、こうすればよい句になるといった考えに疲れて、何気なく見たままの次の句を間に合わせ的に出したところ、先生から高評価頂いたことがあった。
セスナ機もトンボも同じ方へ飛び 妻の足大きく見えし今朝の秋
一旦捨てて虚心でことに臨むと思いがけない成果が生まれるようである。
2025(R7).6.30 ― カエサル(シーザー)と信長の不思議な共通点 ― (第 146 号)
この6月に塩野七生著「ローマ人の物語」の「ユリウス・カエサル ルビコン以後」編(234頁)7回目読了を果たした。この編だけ読む回数が特に多い。
かの世界史の巨人カエサル(シーザー)が紀元前44年3月15日に元老院議場付近でブルータスほかに暗殺された。満55歳であった。カエサルの独走と王制への移行を阻止し、元老院主導の共和政復帰を目指したものであった。実行部隊は14人の元老院議員で隠し持った短剣(本来帯同は許されていなかった)で、気が狂ったように刺しまくり、23箇所の傷を与えたのである(胸に受けた2刃目だけが致命傷)。カエサルは同議員全員から積極的にカエサルを守るとの誓約書を取った直後に護衛隊を解散していたので、この日もまったく無防備であった。
ローマが生んだ唯一の創造的天才と評されるカエサル、地中海全域を掌握し、迅速に数々の改革を断行、強大な権力を手中にして事実上帝政を現実のものとした直後のことであった。なお、この14人は全員が2年以内にカエサルの後継者らによって命を奪われている。
一方、日本の織田信長である。1582年(天正10年)6月21日、京都本能寺において明智光秀の謀反によって寝込みを襲われ、包囲されたことを悟ると、寺に火を放ち、自害して果てた。享年49歳。信長の嫡男で京都妙覚寺に宿泊していた信忠も襲われて自害した。信長と信忠の死によって織田政権は瓦解するが、光秀もまた6月13日の山崎の戦いで羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に敗れて命を落とした。
朝倉・浅井氏さらには武田氏を滅亡させ、天下をほぼ手中にしつつあった信長が、何故突然命を絶たれたのか。中国地方で毛利攻めに当たっていた秀吉の要請を受け、そこに赴く途中ともいわれるが、何故無防備な状態で本能寺に滞在したのか。もっとも家臣である光秀以外にこのようなことをなしうる軍勢は当時当地には存在しなかった。
カエサルも信長もまともに戦えば何者にも負けなかった、絶対的自負があった。しかし個人としての身の安全に関しては、ほれぼれするほど大らかで、人を信ずる、別の側面では人は豹変すること、人は意外な力を発揮することを過小評価していた気がする。東西の歴史の巨人の不思議な共通点である。英雄らしい。
2025(R7).5.31 ― チューリップの秘密 ― (第 145 号)
 |
今年も庭に美しくチューリップが咲いた。長い冬が次第に後退し、春の息吹が庭の隅々に表れ始めるとき、華やかに勢いよく広告塔になるのがチューリップである。色もグループごとにいわぱ思い思いの装いで、光の3原則の赤青黄色を中心に少しずつ混合色が散らばり、色彩展示会のようでもある。
あまりきちんと見ず、俳句や詩的感覚で眺めていた私であるが、朝になると花が開き、夕になるとつぼんでいくということに改めて気付き、何故だろうと考えるに至った。太陽光の強弱に関係するのだろうが、それにしても何千年、何万年と生き抜いてきただけの理由があるのであろうと推測してみたが、不思議の壁を突破できず、とうとうAIならぬネット検索で勉強することにした。
調べてみて感嘆の一言であった。なんという自然の知恵であり、力であろうか。「チューリップの花が日の経過とともに大きくなるのは、規則正しく、朝に開き夕方に閉じる開閉運動をするのが原因です。花びらには、メシベの方を向いている内側の面と、花が閉じたときに花を包み込むように見える外側の面があります。
朝に気温が高くなると、花びらの内側の面が外側の面よりよく伸びます。その結果、花びらは外側へ反り返ります。これが、「開花」という現象です。夕方に気温が下がると、気温が上がったときとは逆に、花びらの外側の面が内側の面よりよく伸びます。すると、反り返っていた花びらの反りがなくなります。その結果、花は閉じます。これが、「閉花」という現象です。
朝に、花びらの内側がよく伸びて、外に反り返り、夕方に、花びらの外側がよく伸びて、花が閉じるのですから、毎日、花は少しずつ大きくなります。チューリップの花は、約10日間、開閉運動を繰り返したあとに萎(しお)れますから、初めて開いた日の花より、約2倍の大きさになることもあるのです。」
この開閉の仕組みを解き明かしたのはイギリスの植物学者のウッドとのことである。1953年の実験なのでそんなに古い話でもない。何故そのような仕組みを選んだのか、生き残るうえでどう役立ったのかなどの説明までは見いだせなかった。
ぼんやりその美しさだけ見ていたが、今では敬意を以って見つめている。「とんでもない ことを企み チューリップ」 保坂 伸秋 (俳句歳時記から)
2025(R7).4.30 ― 5度目の「項羽と劉邦」 ― (第 144 号)
 |
この月に司馬遼太郎作の「項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)」を読み終えた。5回目である。1回目が2015(平成25年)5月の10年前なので2年に1回同じ本を読んでいることになる。書斎でホットくつろいだ時間に何かノンフィクション的小説でしかも歴史の教訓として示唆に富む、そうしたことを作家が語りかけてくる本が無性に読みたくなり、周りには歴史ものがあちこちに積まれている。しかし種切れになってきたとき、何度目であってもどうしても読みたくなるのがこの本と「ローマ人の物語」(塩野七生著)である。他はない。
かつて心象スケッチ「語りかける作家(第84号)」(2013(平成25).8.8)において、「お二人の作家は私たちに語りかけ、問い掛け、考えさせてくれる。作家本人の深い洞察力を通して、歴史の真実と重みそしてそこから導き出される教訓を示してくれる。このような先導者こそ人を育て、世の向かうべき方向を誤りなく示してくれると感ずる。」と述べた。読むたびにその感を強くする。
項羽は、基本的に並外れた体力・気力で周囲を圧倒し、部下兵卒を熱い球にして嵐のように駆け抜け、向かうところ敵なしの武将である。また、名門の出らしく礼儀正しいところがあり、家族・親族・一族を大切にし、敬い、子供っぽい、清らかな感情、何とも言えない優しさを持つ。ただし、敵や敵地の人民を憎めば人の成しがたいような暴虐を働き、何万人も平気で生き埋めにする。
一方の劉邦は、家柄も人脈も教育もない、あるのは立派な顔ひげのみである。家の農業も継がずに町のごろつきのように出没する。ただ、いつの間にか勝手に寄ってくる子分のような者が多くおり、座を作ると劉邦が中心となり、劉邦がいなくなると皆つまらなくなって去る。平気で人の上に立てる。大混乱期に街を守るため中心に祭り上げられると、自分では何もできないが寄ってくる人材を使い、その献言に従い、いつの間にか天下を手中にしてしまった。
人の世で最終的に成功を収めるのは、個人に備わった能力が抜きんでている、一人で何でもできるといったことに起因するよりは、むしろ自己の能力に限りがあることを知り、他の多くの人々の力を結集して乗り切ることができる資質であり、やはり最後は運のようだ。
この本は司馬遼太郎を通じて中国古代というよりは、人間の普遍的なありようと結末を示してくれている。2千年も前にこまめに取材してこの物語の原典ををまとめた司馬遷(SC145~BC86)への敬意もさらに高まった。